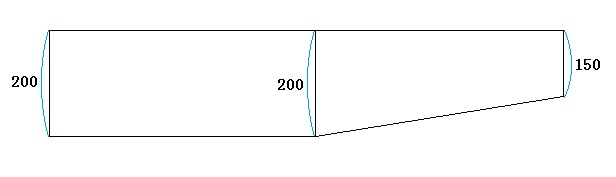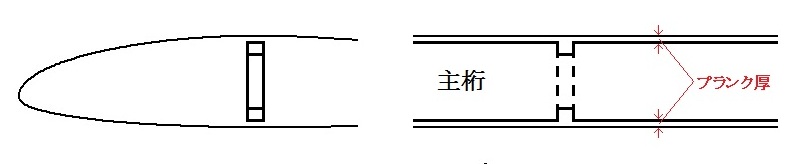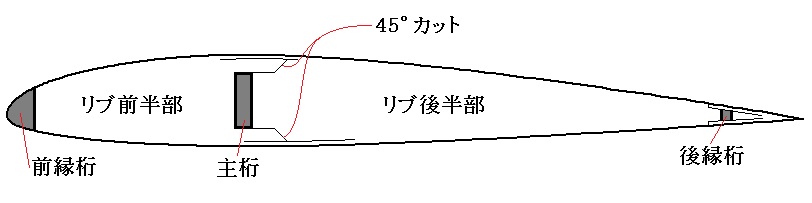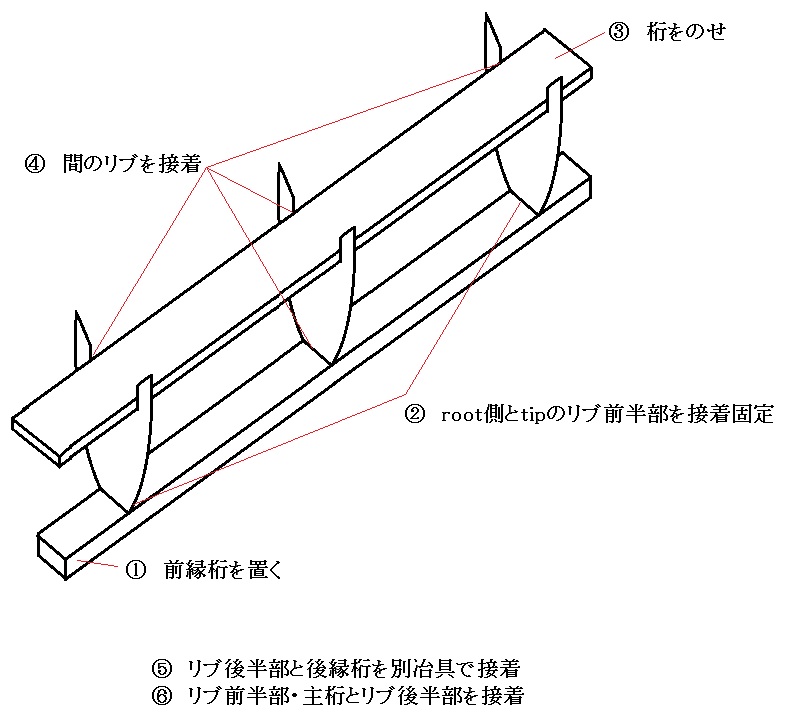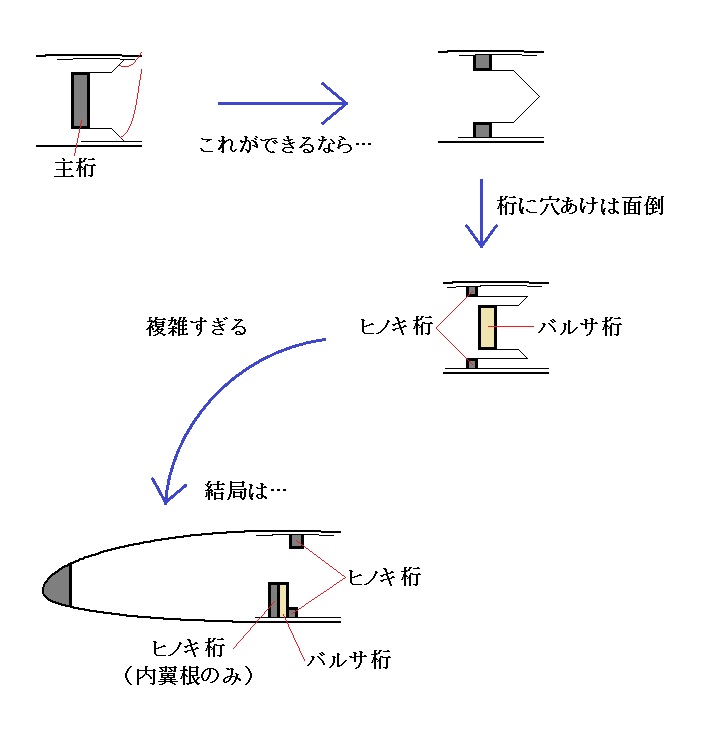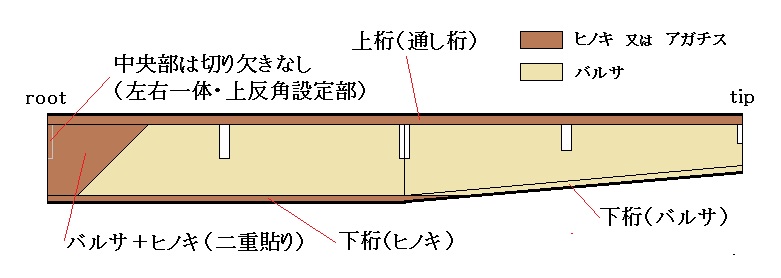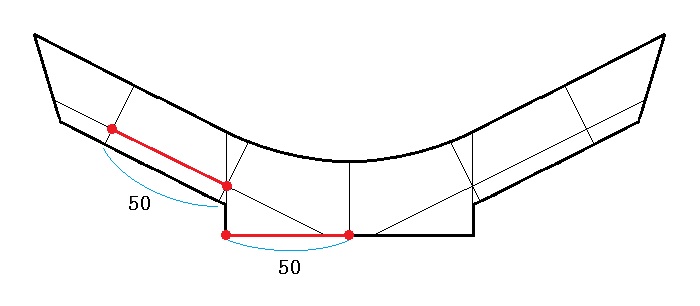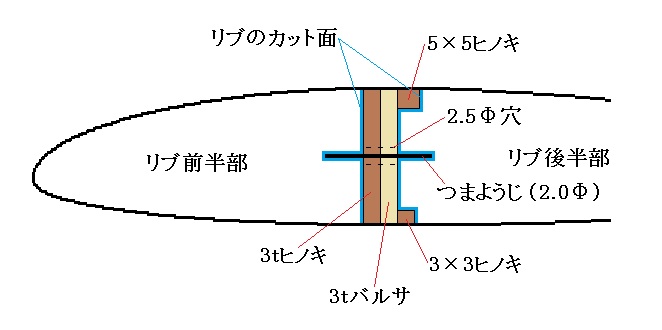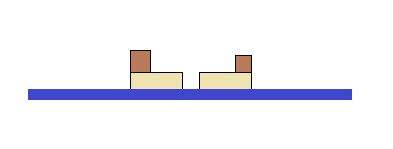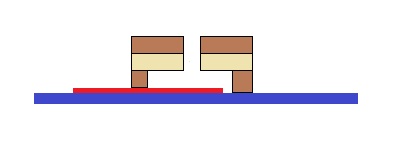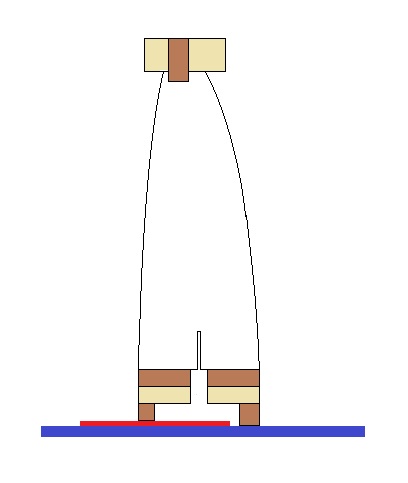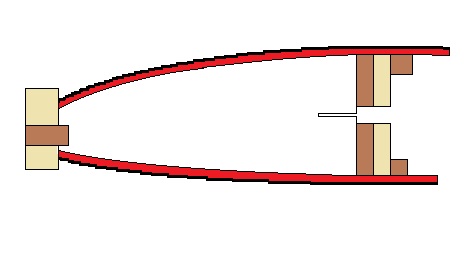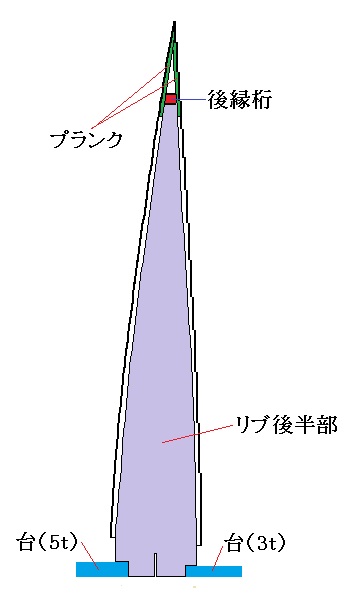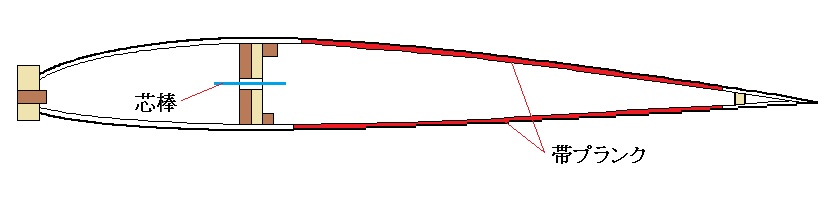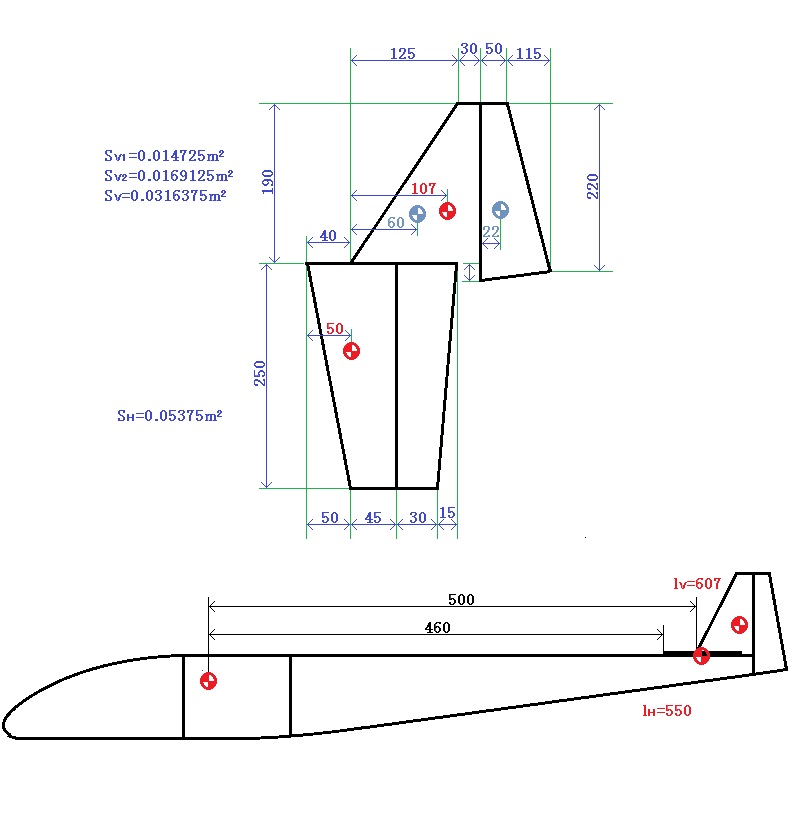Cr = 200 mm、λ = 3/4 → Ct = 150 mm 。
b = 2000 mm とすると、
S = 0.375 m2 、AR = 10.7 。
翼No.5機:S = 0.304 m2 、W = 0.75 kg 時 W/S = 2.47 kg/m2 。
W/S ≦ 2.5 kg/m2 とすると S = 0.375 m2 から W/S ≦ 0.938 kg 。
W = 0.85 kg におさえられるとして、この時 W/S = 2.27 kg/m2 。
主翼の桁とリブの組み方の新方式
製造過程
胴体巾 = 60 cm 。〜とりあえず今の胴体で飛ばす。
主翼桁中央セクション
リブ組みは前半部/後半部を分けて作り、合わせてからプランクをかける方式の方が綺麗に仕上がると思う。
リブのカットは、つまようじ穴( 2 mm 巾)をあけてから前半部と後半部を切り離す。
2.5Φ穴は、どっちみちリブと正確に合わせられないから、もっと大きくてもよい。
(桁荷重のかからない所だから、肉抜き穴としてあけてもよい。)
リブ位置に 2.5Φ穴をあけたバルサ通しウェブにヒノキ桁を接着固定する。
ひっくり返して 2t の台をして、翼根部ヒノキウェブを貼り付ける。
その上に、リブ前半部と前縁桁を接着。
リブ前半部をプランクで覆い、前縁桁を整形。(前半部を完成)
リブ後半部と後縁桁とを組み、後縁プランクを取り付ける。
リブ後半部前端は固定していないのでフラフラしているが、その方がかえって前半部と合わせた時に微妙な調節ができる。
リブ前半部に芯棒を差し込んで接着し、これとリブ後半部を組み合わせ、帯プランクを接着。
尾翼設計
胴体長は、最大でバルサ材長 (900 mm) +先端ブロック分。
→ 胴体長を一定として、尾翼容積は尾翼面積で調整する。
① 「翼No.5」機尾翼の実寸調査。尾翼容積算出。
② 主翼面積が増大していることを考慮して、平面形を仮決定。尾翼容積算出。
③ 「翼No.5」機の尾翼容積と比較しながら、新機の平面形を調整。